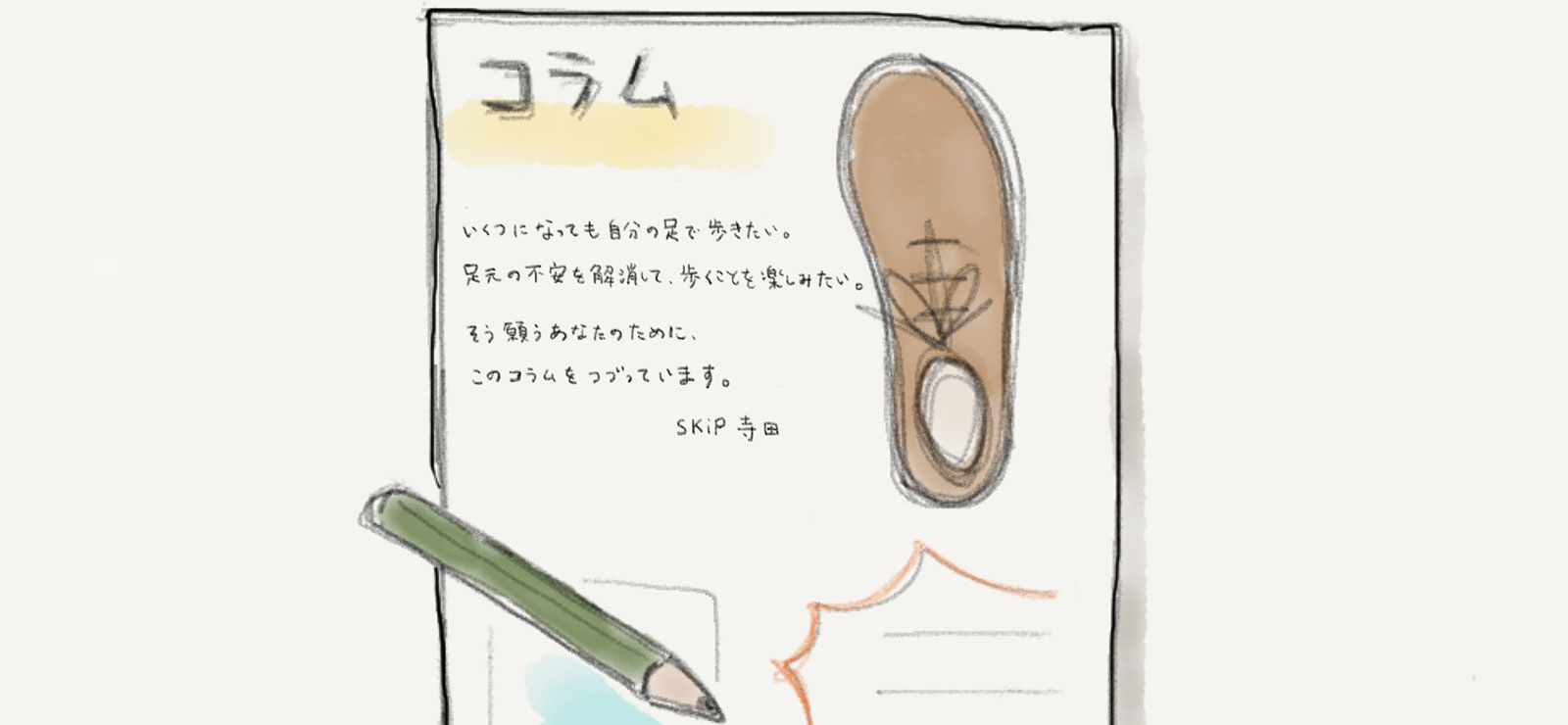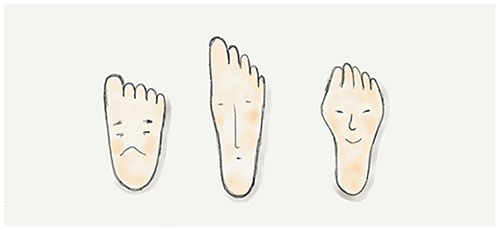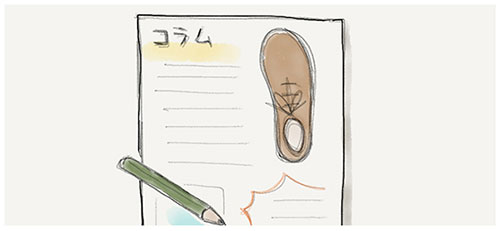【書評】すばらしい人体 〜 病気と健康の境目はどこにあるのか?
世界中を巻き込んだコロナ禍を通じて、誰もがウイルス感染症などの病気や自分自身の健康に関心が深まったのではないでしょうか。
このような健康不安の大きな時代を生き抜くためには、自分の身体のしくみや病気とはどのようなものなのかを知ることが、とても意味のあることだと僕は思います。
そこで今回は、そんなテーマにぴったりの「すばらしい人体」という本をご紹介させていただきます。
本書は、難しい医学の話が、とてもわかりやすく、軽妙な語り口で説明されていて、とにかく面白かったですね。このコラムで、その一端に触れてもらえたら嬉しいです。
それでは、早速参りましょう!
□著者
山本健人先生(やまもとたけひと)
2010年、京都大学医学部卒業。医学博士。
外科専門医、消化器病専門医、消化器外科専門医、がん治療認定医など。
医療情報サイト「外科医の視点」を運営。
著書に「医者が教える正しい病院のかかり方」「がんと癌は違います〜知っているようで知らない医学の言葉55」「医者と病院をうまく使い倒す34の心得」「もったいない患者対応」ほか多数。
医学を学ぶことは、途方もなく楽しい。
私が医学生の頃から絶えず味わってきた興奮を、誰かと共有したい。多くの人に伝えたい。
そんな思いで本書を執筆されたそうです。
□こんな方におすすめ
本書は、
・健康で長生きしたい
・体のしくみに興味がある
といった方におすすめします。
□面白かったポイント
個人的に面白かったポイントを3つご紹介します。
①私たちの体は重い
私が初めて医療現場に出たときにもっとも驚いたのは、「人体がいかに重いか」という事実。
全身麻酔中に体を移動させるときは、手と足それぞれを誰かがしっかり支えていないと、重みのままに勢いよく垂れ下がり、あっという間に関節を損傷してしまう。
と山本先生。
私たちの体は、体重が50キロの人であれば、頭は5キロほど、腕はそれぞれ5キロほど、足はそれぞれ10キロずつあるそうです。頭や片方の腕が5キロの米袋と同じぐらいの重さがあると想像してみてください。
意外なほどずっしりと重いことがわかると思います。
ここでもしよかったら、家族や友達とペアになって、力を抜いた状態の腕や脚がどれぐらい重いのか、お互いに確かめ合ってみてください。
②健康な人が床ずれにならない理由
なぜ健康な人は体に床ずれができないのかご存じですか?
その理由は「無意識に」寝返りを打っているからです。
自力で寝返りが打てないと、あっという間に床ずれができてしまうそうです。
お尻やかかと、肘、肩甲骨や後頭部などは、かなりの重みがかかり、床ずれのできやすい部位。 病院や介護施設では、看護師や介護スタッフが、重い病気や寝たきりで動けない人が床ずれを予防するために、定期的に体勢を変えるケアを行なっているんですね。
「私たちは普段、健康であることのありがたみになかなか気づけない。ひとたび病気になり、それまで「無意識に」行っていたことができなくなると、途端に全身に不具合を起こしてしまう。「何も考えずに楽な姿勢をとれること」は、健康な人が持つありがたい機能です」
と山本先生。
僕も自分や家族が健康でいられることに感謝して、日々過ごしていきたいなと思いました。
③病気と健康の境目はどこにある?
細菌は私たちに病気を引き起こす微生物である。
では、細菌が体の中に入った状態は病気か、というとそうではない。
そもそも私たちの皮膚や口の中、腸の中も細菌だらけである。これらの細菌が体に何らかの不具合を起こしたとき、初めて病気と呼ぶことができる。
と山本先生。
つまり「細菌がいるかいないか」が「病気か健康か」を決めるのではない、ということですね。
例えば、口唇ヘルペスという、口の周りに腫れものができて痛みを伴う病気がありますが、
このウイルスは普段から顔にある神経節に住みついていて、疲れが溜まったときなどに暴れ出し、口唇ヘルペスを引き起こします。
つまり、「ヘルペスウイルスが体内にいる状態」は健康そのもので、「口の周りに不快な症状を起こしたとき」のみ「病気」とみなします。
病気の代表格のガンも同様で、健康な人の体にも絶えずがん細胞は生まれていて、免疫によって排除されています。
つまり、がん細胞が体にある状態は「がん」という病気ではないということです。
がん細胞が命を脅かすポテンシャルを持ったとき、初めて病気と見なされ、医療が介入します。
そう考えると、日頃から良質な食事や睡眠、そして適度な運動をする生活を心がけて、免疫力を下げないことがいかに重要かがわかりますね。
ということで、個人的に面白かったポイントを3つご紹介させていただきました。
□まとめ
今回ご紹介した内容以外にも、
・オナラとウンチを出し分けられる仕組み
・肘をぶつけるとなぜ電気が走るのか?
・免疫やワクチンの仕組み
・血液はどうして赤いのか?
など、興味がそそられるような魅力的な内容が盛りだくさんの本書。
健康とは何か?自分の身体はどう成り立っているのか?ということへの理解が深まり、もっと人体について知りたい!自分自身について知りたい!そう思わせてくれた1冊でした。
このコラムをご覧になっているあなたに、ぜひ本書をおすすめします。
ということで、今回の話は以上です。
【参考文献】
本書の巻末に掲載されていた『人体・医学に興味を持った人たちにお勧めしたい本』は以下のとおりです。
ご参考になさってください。
関連記事
【コラム】固有感覚って、なに? 〜 足裏のセンサー"を目覚めさせる話 〜
固有感覚とはどのようなもので、足裏のセンサーを目覚めさせることがなぜ大事なことなのか、ということをつづりました。

【5分解説#5】心が豊かになる歩き方
今回も引き続き「病気の9割は歩くだけで治るpart2」という本の中から、「心が豊かになる瞑想歩行」というところの話を解説します。

【5分解説#4】インターバル速歩のススメ
今回も引き続き「病気の9割は歩くだけで治るpart2」という本の中から、「インターバル速歩のススメ」というところの話を解説します。

【5分解説#3】ウォーキングで免疫力アップ!〜 骨ホルモンの話 〜
今回も引き続き「病気の9割は歩くだけで治るpart2」という本の中から、「骨から長寿ホルモンが出ていた!」というところの話を解説します。

【5分解説#2】ヒトの寿命は歩くだけで変えられる!? 〜 染色体・テロメアの話 〜
今回も引き続き、長尾先生の「病気の9割は歩くだけで治るpart2」という本の中から、『「人間の最長寿命は120歳」は誰が決めた?』というところの話を解説します。

【5分解説#1】老化予防とウォーキングの関係とは? 〜 病気の9割は歩くことで治る!part2 〜
今回から5回に分けて、以前ご紹介させていただいた「病気の9割は歩くだけで治る!」という本の続編にあたる「病気の9割は歩くだけで治る!part2」という本をご紹介させていただきます。